「牛にひかれて善光詣り」はあまりにも有名な言葉です。
「思いがけないことが縁で良い方に導かれること」という意味で使われますね。
「牛にひかれて善光寺詣り実行委員会」もあります。
国宝や重要文化財がたくさんある善光寺は無宗派のお寺で、全ての人を受け入れるお寺として有名です。
七年に一度の「御開帳」もニュースになりますね。
ご本尊の「一光三尊阿弥陀如来」は日本最古の仏像だそうですよ。
お寺の中を巡るとご利益がありそうです。
パワースポットとしても人気なので年間の参拝者は700万人を超す、信州を代表する観光名所ですよ。
となれば周辺にはすてきなお店が並びます。
いろんな意味で行ってみたい善光寺。
暖かくなったら、信州小諸の街に行ってみたいな。
Contents
善光寺はなぜ有名なのでしょう?!
善光寺は、日本の長野県松本市にある仏教寺院であり、
数百年にわたって信仰と歴史の中心地として知られています。
その有名さの理由はいくつかあります。
まず、善光寺は平安時代に遡る歴史を持つ古刹です。
伝承によれば、善光寺は7世紀に建てられたとされ、国宝である本堂も8世紀に造られたものです。
その歴史的な背景と建築の美しさにより、多くの人々が善光寺を訪れています。
また、善光寺は信仰の対象となっている弥勒菩薩(阿弥陀如来)を祀っていることでも知られています。
弥勒菩薩は、来世で救済を与えるとされ、善光寺はその教えを広く伝える場となっています。
この信仰の根強さが、善光寺の有名さの一因です。
さらに、善光寺は「お遍路さん」として知られる巡礼者の目的地のひとつでもあります。
信仰心や冒険心から、各地の寺社を訪れる遍路をする人々が多く集まります。
善光寺は、遍路道の中でも有数の名所であり、その独特の雰囲気と美しさが多くの人々を魅了しています。
以上のような理由から、善光寺は日本国内外で広く知られ、多くの人々に愛されている寺院となっています。
善光寺は一度は聞いたことがあることわざで有名!!
「牛にひかれて善光寺」。
むかしむかし、不信人なおばあさんがいました。
おばあさんが川で布を洗っていたら、どこからか牛がやってきて大事な布を角に引っ掛けて走り出しました。
おばあさんがあわてて追いかけると、牛は善光寺に入っていきました。
後について入っていくと、善光寺の仏さまの光で牛のよだれが文字に見えました。
「牛とのみ 思いすごすな 仏の道に 汝を導く 己の心を」と読めました。
おばあさんは仏さまを信じて覚りを求める心を起こしました。
その後、お婆さんが家の近くの観音堂にお参りしたら、観音様の足元におばあさんの布がかけてありました。
「ああ、あの時に牛だと思ったのは観音様の化身だったのだ」と気づき、ますます善光寺の仏さまを信じました。
そして極楽往生をとげました、とさ。
現在では「思いがけないことが縁で良い方に導かれること」という意味で使われます。
善光寺はなんの神様が祀られていてどんなご利益がある?
善光寺は仏教寺院なので、特定の神様が祀られているわけではなく、
本尊として阿弥陀如来を奉っています。
善光寺の阿弥陀如来像は、「ほんまもの(本真物)」と称され、仏像としては国宝に指定されています。
善光寺にはさまざまなご利益がありますが、
特に「眼病平癒」(眼病の治癒)や「開運除災」(運気上昇と災厄除去)のご利益があるとされています。
また、随願寺(願い事を叶える寺)としても知られていて、様々な願い事を叶えてくれると信じられています。
善光寺はまた、弘法大師空海が定めた八十八ヶ所巡礼の模範とされており、信者による参拝の地となっています。
そうした理由から、「真言密教の道場」としても知られており、仏教修行の地としても重要な位置づけがなされています。
善光寺はパワースポットで有名!!
「遠くとも一度は詣れ善光寺」と江戸時代から言われているそうです。
一度でもお詣りをしたら「来世・現世にご利益がある」「極楽往生できる」と聞けば、行きたくなりますね。
善光寺の本堂を拝もう!
本堂は「国宝」に指定されています。
また、撞木造(しゅもくづくり)といって屋根はT字型になっています。
とても珍しい形です。
宗派を問わない「無宗派」なので、みんなお詣りしやすいのですね。
しかも「御印文頂戴(ごいんもんちょうだい)」という行事が1月7日から15日まで行われます。
善光寺の宝印を額に押してもらうのです。そして御印文を頂戴すれば、極楽浄土が約束されるといわれているのです。
なんて素敵!!
善光寺の御朱印をいただこう!
20種類ほど御朱印を頂けます。
美しい御朱印です。
もちろん御朱印帳も揃っていますよ。
善光寺のお戒壇巡りをしてみよう!!
瑠璃壇の下の回廊を手探りで進むのが「お戒壇巡り」といいます。
それは死の疑似体験でもあり、生まれ変わることを意味しているといわれます。
「極楽の錠前」に触ったら極楽往生できるそうです。
善光寺の経蔵に行ってみよう!!
経蔵には、仏教経典の全てを網羅した「一切経」が収められています。
中央に、輪蔵(りんぞう)と呼ばれるものがあり、腕木を押して回転させると、経典を全て読んだことと同じ功徳が得られるのだそうです。
なんてありがたい!!
善光寺は7年に1度の「御開帳」でも有名です!!
[st-minihukidashi fontawesome=”” fontsize=”” fontweight=”” bgcolor=”#f3f3f3″ color=”#000000″ margin=”0 0 20px 0″ radius=”” position=”” myclass=”” add_boxstyle=””]御開帳って何だろう?[/st-minihukidashi]![]()
[st-mybox title=”” fontawesome=”” color=”#757575″ bordercolor=”#BDBDBD” bgcolor=”#f3f3f3″ borderwidth=”0″ borderradius=”5″ titleweight=”bold” fontsize=”” myclass=”st-mybox-class” margin=”25px 0 25px 0″]
絶対秘仏の「一光三尊(いっこうさんそん)阿弥陀如来像」と同じ姿をした前立(まえだち)本尊を公開する儀式です。本堂正面に立つ回向柱(えこうばしら)に触れたら、前立本尊とつながることができて、功徳があるといわれます。[/st-mybox]
[st-minihukidashi fontawesome=”” fontsize=”” fontweight=”” bgcolor=”#f3f3f3″ color=”#000000″ margin=”0 0 20px 0″ radius=”” position=”” myclass=”” add_boxstyle=””]回向柱って何ですか?[/st-minihukidashi]![]()
[st-mybox title=”” fontawesome=”” color=”#757575″ bordercolor=”#BDBDBD” bgcolor=”#f3f3f3″ borderwidth=”0″ borderradius=”5″ titleweight=”bold” fontsize=”” myclass=”st-mybox-class” margin=”25px 0 25px 0″]
御開帳の時に立てられる柱です。回向柱の奉納は江戸時代から続く習わしだそうです。
幕府が松代藩に善光寺本堂の再建を命じたことが始まりで、旧藩内から寄進しています。
令和3年の回向柱は樹齢約150年の大杉だったそうです。[/st-mybox]
善光寺前の仲見世も有名ですよ!!

引用善光寺
長野といえば「おやき」ですね!!
小麦粉やそば粉を練った生地に、小豆や野菜で作った餡をくるんで焼いたものです。
長野県の郷土料理になっています。
長野だけでなく、気候や地形等の関係で米作りに適さない所で作られています。
仲見世には素敵なお店、寄りたくなるお店が並んでいます。
お食事、スイーツ、お土産、何でもありますが「おやき」のお店を紹介します。
引用喜世栄
他にも「みそソフト」「みそプリン」など聞いただけで「絶対食べたい」と思うものがたくさんあります。
長野県は味噌作りでも有名です。「信州みそ」ですね。
見た目は淡色で、辛口です。
日本全体で生産・消費されている味噌の約半分が「信州みそ」ですって!!
長野県内にみそ蔵が100軒もあるそうですよ!
それぞれのみそ蔵は「試食できる」「みそ作り体験できる」「見学できる」「お食事ができる」など、特徴を出しています。
[st-minihukidashi fontawesome=”” fontsize=”” fontweight=”” bgcolor=”#f3f3f3″ color=”#000000″ margin=”0 0 20px 0″ radius=”” position=”” myclass=”” add_boxstyle=””]みそ蔵巡りをしたら楽しそう!![/st-minihukidashi]![]()
食べ歩きもでるようなので、お行儀に気を付けて食べながら散策してみたいですね!
本堂へ続く石畳は7,777枚もあるそうですよ!!
どこから運んできて敷き詰めたのか、興味があります。
でも数える勇気は…?
善光寺のすごい歴史に触れてみよう!!
引用善光寺
善光寺の御本尊は日本最古です!
善光寺のご本尊は「一光三尊阿弥陀如来(いっこうさんぞんあみだにょらい)」です。
日本最古の仏像です。
インドから朝鮮半島の百済国へ渡り、552年に仏教が日本に伝わったときに百済から日本へ伝えれられたそうです。
善光寺が始まってから約1400年以上、深い信仰を得ています。
[st-minihukidashi fontawesome=”” fontsize=”” fontweight=”” bgcolor=”#f3f3f3″ color=”#000000″ margin=”0 0 20px 0″ radius=”” position=”” myclass=”” add_boxstyle=””]そんな文献が残っているなんてびっくり!![/st-minihukidashi]![]()
善光寺の梵鐘は長野冬季オリンピック開会式で有名に!!
1998年(平成10年)に長野冬季オリンピックが行われました。
その開会式で善光寺の梵鐘が世界平和の願いを込めて鳴り響きました。
この鐘にはすごい歴史があります。
上杉謙信と武田信玄は川中島の合戦で戦いました。1553年のことです。
この時武田信玄は善光寺如来や本尊、梵鐘から仏具まで甲府に移したといいます。
そして新しく「甲斐善光寺」を甲府に建てました。
重さ150キロもある鐘を長野から甲府まで運んだというのです。
その時に傷がたくさんついたので「ひきずりの鐘」といわれるそうですよ。
その後も善光寺の御本尊は戦国時代に各地を転々とし、40年後に信州に戻りました。
[st-minihukidashi fontawesome=”” fontsize=”” fontweight=”” bgcolor=”#f3f3f3″ color=”#000000″ margin=”0 0 20px 0″ radius=”” position=”” myclass=”” add_boxstyle=””]鐘の音を聞いて歴史を感じたい![/st-minihukidashi]![]()
引用善光寺
善光寺は実はたくさんある?!
現在200以上の「善光寺」が各地にあります。
その理由は…。
鎌倉時代に「善光寺聖」が全国に善光寺信仰を広めたから、だそうです。
この方は正規の寺院を離れて諸国をまわる僧侶です。
善光寺聖が善光寺如来の分身を背負って信仰を広めたのです。
江戸時代には信州の善光寺から前立本尊が出張する「出開帳」が行われるようになりました。
(善光寺本堂で行われるのは7年に1度の「御開帳」です。)
こうやって善光寺は各地に広まったというわけです。
善光寺はいつ、誰が建てたの??
642年に「本田善光(よしみつ)」さんが建てたといわれます。
諸説ありですが…。
推古天皇の勅命で本田善光さんの自宅が新造されました。
本田善光さんはそれを自宅兼寺として「善光寺」と名付けたそうなのです。
[st-minihukidashi fontawesome=”” fontsize=”” fontweight=”” bgcolor=”#f3f3f3″ color=”#000000″ margin=”0 0 20px 0″ radius=”” position=”” myclass=”” add_boxstyle=””]天皇の勅命で家を作るなんてすごい人!![/st-minihukidashi]![]()
その後火事や戦で何度も焼失、再建を繰り返しました。
本当に諸説ある感じなのですが、もう一つの説としては、
信濃国(長野県を含む旧国名)の豪族である信濃源氏の一族によって、
平安時代後期の850年頃に建立されました。善光寺の建立のきっかけについては、伝説があります。
伝説によれば、一族の祖先である真田氏が、恐ろしい病にかかっときに、修行僧が現れて、
その人を救ってくれたことがきっかけで、真田氏がその地に寺を建てたといわれています。
その後、鎌倉時代に入ってからは、日蓮宗の総本山として栄えるようになりました。
善光寺は建立当初は違う名前だったという説がありますが。。
善光寺は建立当初からその名前で呼ばれていました。ただし、
当時は「諏訪の坊(すわのぼう)」と呼ばれており、平安時代後期の創建以来、
約600年間にわたってその名が使われていました。しかし、鎌倉時代に日蓮宗が創立されると、
日蓮宗の開祖である日蓮聖人が善光寺に滞在し、その教えを説いたことから、「善光寺」と改名されました。
善光寺という名前の由来について
「善光寺」という名前の由来については、いくつか説がありますが、
一般的には以下のような説があります。 一つは、日蓮聖人が善光寺に滞在していたとき、
霊験があったという話。日蓮聖人が善光寺に滞在中、火災が発生し、火事で寺が全焼してしまう危機に陥りました。
日蓮聖人が祈りを捧げると、天から不思議な光が現れ、一瞬で火災が収まったという話が伝えられています。
このエピソードから、「善光(ぜんこう)」という名前が付いたという説があります。
もう一つは、善光寺の周辺には各地から多くの巡礼者が集まっていました。
これに対して、平安時代の詩人・藤原行成が「衆人が集まる(眾餘集つ)ところ」という意味で、
「善光(ぜんこう)」と名付けたという説もあります。 いずれにせよ、善光寺という名前は、長い歴史の中で、
信仰や歴史上の出来事などが重なって、いくつかの説が生まれたのだと思われます。
善光寺にはどんなお宝があるのですか?
善光寺には多数の重要文化財や国宝が収蔵されています。
ここでは、代表的なものを数点ご紹介します。 まず、国宝に指定されている客殿があります。
この建物は、江戸時代初期に建てられたもので、江戸時代後期には藩主や公卿の多数の寄進によって、
内部に多くの宝物が寄進されました。その中には、難読漢字の大日経典や、
万葉集を全て収めた万葉集影印本などが含まれており、非常に貴重な宝物とされています。
また、重要文化財に指定されている飛雲閣には、多数の絵画や書跡、古文書、仏像などが収蔵されています。
中でも有名なのは、平安時代の巻物絵画である「絹本著色法華経」や「紙本著色般若経」、
鎌倉時代の金堂内菩薩像、弘法大師空海自筆の「十界曼荼羅」などです。
他にも、善光寺には数多くの宝物が展示されています。また、蘭学者であった塩原丹波守が寄贈した
「蘭学写本展示室」には、18世紀から19世紀のオランダ語の解剖学書や地図、植物図鑑などが展示されています。
いやあ、とっても、貴重なものがたくさん収められているわけですね。
善光寺にはすごい人たちがいらっしゃいました!!
1214年には親鸞聖人が参詣したという記録もあります。
1714年には7777枚の参道の敷石ができました。
2010年にはダライ・ラマ法王が来寺して世界平和のための法要をされました。
[st-minihukidashi fontawesome=”” fontsize=”” fontweight=”” bgcolor=”#f3f3f3″ color=”#000000″ margin=”0 0 20px 0″ radius=”” position=”” myclass=”” add_boxstyle=””]すごいお寺なんですね!![/st-minihukidashi]![]()
善光寺の七名物は?!幻のものも!!




[st-mybox title=”” fontawesome=”” color=”#757575″ bordercolor=”#BDBDBD” bgcolor=”#f3f3f3″ borderwidth=”0″ borderradius=”5″ titleweight=”bold” fontsize=”” myclass=”st-mybox-class” margin=”25px 0 25px 0″]七名物その一*七味唐辛子*日本三大七味唐辛子のひとつです。[/st-mybox]
[st-mybox title=”” fontawesome=”” color=”#757575″ bordercolor=”#BDBDBD” bgcolor=”#f3f3f3″ borderwidth=”0″ borderradius=”5″ titleweight=”bold” fontsize=”” myclass=”st-mybox-class” margin=”25px 0 25px 0″]
七名物その二*善海の田楽*罪を犯したある人が反省して仏門に入りました。「善海」と名乗って旅人にみそ田楽を作って提供したそうです。[/st-mybox]
[st-mybox title=”” fontawesome=”” color=”#757575″ bordercolor=”#BDBDBD” bgcolor=”#f3f3f3″ borderwidth=”0″ borderradius=”5″ titleweight=”bold” fontsize=”” myclass=”st-mybox-class” margin=”25px 0 25px 0″]
七名物その三*雲切目薬*1543年、ポルトガル人から目薬の作り方を教わった人が販売しました。[/st-mybox]
[st-mybox title=”” fontawesome=”” color=”#757575″ bordercolor=”#BDBDBD” bgcolor=”#f3f3f3″ borderwidth=”0″ borderradius=”5″ titleweight=”bold” fontsize=”” myclass=”st-mybox-class” margin=”25px 0 25px 0″]
七名物その四*練り膏薬*固形の外用薬ですが、残念ながら今はありません。[/st-mybox]
[st-mybox title=”” fontawesome=”” color=”#757575″ bordercolor=”#BDBDBD” bgcolor=”#f3f3f3″ borderwidth=”0″ borderradius=”5″ titleweight=”bold” fontsize=”” myclass=”st-mybox-class” margin=”25px 0 25px 0″]
七名物その五*ろうそく*善光寺門前のお店だったそうですが、残念なことに今はありません。[/st-mybox]
[st-mybox title=”” fontawesome=”” color=”#757575″ bordercolor=”#BDBDBD” bgcolor=”#f3f3f3″ borderwidth=”0″ borderradius=”5″ titleweight=”bold” fontsize=”” myclass=”st-mybox-class” margin=”25px 0 25px 0″]
七名物その六*鐘鋳(かない)川端のまんじゅう*鐘鋳川沿いにまんじゅう屋がたくさん並んでいました。今残るのは一軒だけになりました。[/st-mybox]
[st-mybox title=”” fontawesome=”” color=”#757575″ bordercolor=”#BDBDBD” bgcolor=”#f3f3f3″ borderwidth=”0″ borderradius=”5″ titleweight=”bold” fontsize=”” myclass=”st-mybox-class” margin=”25px 0 25px 0″]
七名物その七*三国一の甘酒*麹と米だけで作られている素朴な甘酒です。日本・中国・インドの三国で一番、という意味だそうです。[/st-mybox]
「善光寺はなぜ有名?!牛にひかれて行ってみよう!信州小諸の町!!」のまとめ

- 「牛にひかれて善光寺」ということわざで有名
- 善光寺はパワースポットで有名①本堂は国宝 ②御朱印がたくさんある ③お戒壇巡りも有名 ④経蔵も有名
- 善光寺は7年に1度の「御開帳」が有名
- 善光寺前の仲見世も有名
- 善光寺の歴史はすごい
- 善光寺という名のお寺は全国にたくさんある
- 善光寺の御本尊は日本最古
- 善光寺には「七名物」がある
いかがでしたか?
御利益がたくさんある、歴史もすごい善光寺。
人がたくさん集まれば仲見世も流行る。
おいしいお店もたくさんあり、長野県の名産も手に入る、となれば行きたくなります。
宗教に関心が薄い人も困ったときは手を合わせる私たち日本人です。
春、少し暖かくなったら旅に出てみませんか?









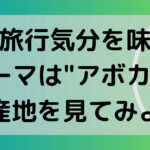
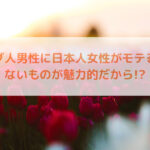
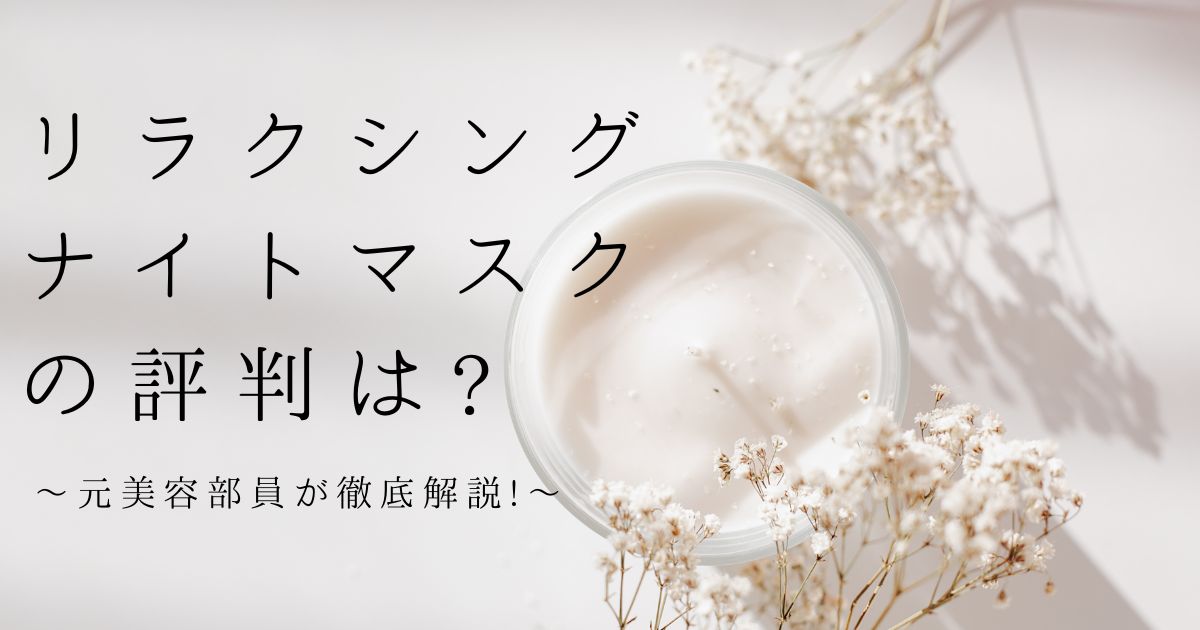

コメント